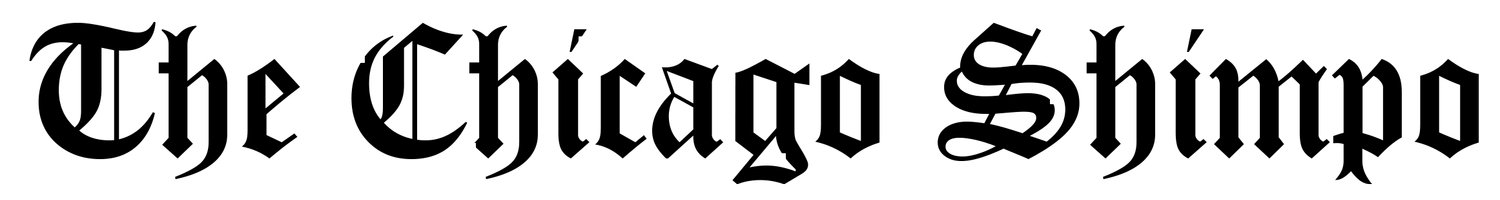クリーニング業界に役立つ機械を、サンコーシャU.S.A. 30周年を祝う
30年の努力を祝い、将来に向けてチームの気勢を上げるサンコーシャU.S.A.プレジデントのウェスリー・ネルソン氏(中)
サンコーシャU.S.A., Inc.が創立30周年を迎え、11月15日にオープンハウスと記念祝賀会が行われた。シカゴのノースウェスト郊外、エルクグローブにあるサンコーシャU.S.A.は、クリーニングのプレス機や乾燥してシワを取る最終工程の機械の販売に特化した会社で、本社は東京八王子に本拠を置く(株)三幸社。同社はタイと中国にも工場を持つ。
オープンハウスでは、ワイシャツの袖と襟をプレスし、シャツのボディをプレスし、同時に両袖に蒸気を通してしわを取り仕上げるという、目の覚めるような一連の工程のデモンストレーションが行われていた。また、ジャケットやズボンもプレスと蒸気で短時間で仕上げるデモンストレーションも行われていた。
▲ シャツのプレス機 ▲ 背広やジャケットのプレス機 ▲ プレス機を説明する梅谷昌樹氏
別室では新規開発されたノンプレスフィニッシャーの紹介が行われた。これは、水洗いした衣類を熱風により、プレスを必要としない仕上げ・乾燥を実現したもので、ズボン、スカート、ワンピース、ユニフォームなどに対応し、高い汎用性を持つ。コンベアーのチェーンに、濡れた衣類をハンガーにかけて吊るすだけで、衣類は自動的に機械の中に運ばれて行き、機械を通過した衣類は仕上がった状態で出て来る。衣類の連続仕上げができ、人手を最小限に抑えることができる。
▲ 連続運営ができるノンプレスフィニッシャー
三幸社は、クリーニング店の店主だった打越満幸によって1977年に創立された。家族運営のクリーニング店の重労働を知り抜いていたからこそ、痒い所に手が届くような仕上げ機械を作ることができた。中小クリーニング店をターゲットに機械製造・販売業をスタートさせた三幸社は、耐久性、品質、安定性を重視した製品開発により、今や日本国内外でトップのシェアを持つ仕上げ機メーカーとして成長した。
シャンバーグにあるシャウズ・クラブハウスで行われた祝賀会では、サンコーシャU.S.A.プレジデントのウェスリー・ネルソン氏が円陣を組んでチームの気勢を上げた。
三幸社の打越圭介副社長
また、三幸社の打越圭介副社長が「30年前、我々は米国での販売に行き詰っていましたが、皆様のサポートのお陰で今日を迎えることができました。皆様のサポートがなければ、また、創業者の英語教師だったネルソン氏がいなければ、サンコーシャU.S.Aを開くことはできませんでした。長年の苦闘もありましたが、皆様とのビジネスのお陰で今日のポジションを築くことができました。今日の30周年を皆様と祝えるのを大変嬉しく思います。今宵は楽しく過ごして下さい」と挨拶した。
クリーニング業界の変遷と機械メーカーの役割
機械の提供でクリーニング業界の助けとなる
三幸社も米国拠点のサンコーシャU.S.A.も今日があるのは「ミラクルだ」と語る打越圭介副社長に、クリーニング業界の変遷とそれに対応する機械のニーズについてお話を伺った。
1970年代から80年代にかけて、日本では家族で運営するような小さなクリーニング店が増えていた。圭介氏の父・打越満幸氏も街のクリーニング屋さんとして毎日10時間ほどアイロンがけをやっていた。一日中立ちっぱなしで重たいアイロンをかけるのは重労働で「儲かるかも知れないが、その前に死んでしまう」と言われた時代だった。
この様な日々の中で、満幸氏は重労働を軽減する方法を考えた。アメリカから中古の仕上げ機を購入して使ってみると、確かに便利だった。一方、アメリカの機械は大きく、背が低い日本人には使いづらい。また、日本人の衣類はアメリカ人の衣類よりも小さく、仕上げ機に合わなかった。どうしたものかと思案した満幸氏は、自分で作ろうと思い立った。
毎晩夕食を済ませるとガレージに行き、アメリカ製の仕上げ機を調べ、自分で図面を引き、狭い日本のクリーニング店にも設置できるコンパクトな仕上げ機を試行錯誤で作り上げた。このような仕上げ機は、まさに日本のクリーニング店が欲するものだった。
中小クリーニング店の苦労を知り抜いていた満幸氏は、その様なクリーニング屋さんがもっと楽になるようにと、中小店向けの仕上げ機の製造販売会社、三幸社を1977年に設立した。ニーズに合った満幸氏の仕上げ機の販売は好調で、三幸社は成長して行った。
1988年に、三幸社はイギリスのバーミンガムで開催されたクリーニング機の展示会に、初めて満幸氏の仕上げ機を出品した。この展示会で高評価を受けた満幸氏について圭介氏は「海外で売れるという確信を本人は持ったんですね。日本でこれだけ行けるんだから、アメリカでも行けるだろうというぐらいの気持ちだったんですよ。マーケティングもしないで、よくもアメリカに会社を出したもんだなと思います。成功はミラクルでした」と語る。
だが、そこには人材との出会いがあった。海外進出を視野に入れた満幸氏は、54歳で英語の勉強を始めた。英会話学校に依頼し、英語教師として来てくれたのがウェスリー・ネルソン氏だった。英語の勉強の傍ら、三幸社の英語版のカタログ作りなどを手伝ってもらっているうちにネルソン氏は三幸社のビジネスに興味を持ち、ネルソン氏の人間性を見た満幸氏は三幸社のアメリカ進出を考え、ネルソン氏を同社に迎えた。入社したネルソン氏は機械工場に約4年間入り、同社の製品を熟知した。そして1993年に流通のハブであるシカゴ地区郊外にサンコーシャU.S.A.をオープンする運びとなった。
アメリカのクリーニング業界は創業百数十年という老舗もある。いずれにしても、日本のクリーニング文化はアメリカから来ており、アメリカはクリーニング機械の本家でもある。そのアメリカで、サンコーシャU.S.A.はどの様にビジネスを開拓して行ったのだろうか。
アメリカのクリーニング業の最盛期は1960年代から70年代だった。「例えばアメリカで1ミリオンの売上げを上げを上げようとすれば、100人の働き手が必要だった。2ミリオンならば200人、3ミリオンならば300人というような時代だった、特に60年代は」と圭介氏は話す。だが公民権運動が広がり、労働賃金も上がって行った。また1980年以降、衣服のカジュアル化が始まった。これによりクリーニング店に持ち込むスーツやドレスの数は減少して行った。
このような社会の変化により、クリーニング業界の売上げは低下傾向となり、1ミリオンの売上げを25人で出すにはどうすればよいかと考えるようになった。このような背景により、アメリカのクリーニング業界では機械化が進んだ。
プロモーションをかけなくても客が来て儲かっていた時代は過ぎ、クリーニング店は生き残るために人員削減を考えなければならなかった。たくさんあったアメリカ人経営のクリーニング店は機械導入を検討する一方、利益減少により店を売却するようになった。そこにアメリカに入植していた韓国人たちが売りに出たクリーニング店を買う事になった。
このようにアメリカのクリーニング業界が下向きになったのが1990年代の初期で、中小のクリーニング店が人員削減による生き残りを模索していた時期に満幸氏のコンパクトサイズの仕上げ機がぴったりとフィットした。
しかし、1993年に進出したサンコーシャU.S.A.は当初、苦戦した。アメリカの大手クリーニング業界はコンパクトな日本製仕上げ機に関心を示さず、最初の半年余りは1台も売れなかった。そこで道を開くきっかけとなったのが、中小クリーニング店を始めていた韓国の人達だった。そして、やがて人員削減による利益拡大を模索するアメリカ人マーケットにも参入することができ、30年が経った今ではアメリカでもトップシェアを持つ会社となった。
圭介氏はネルソン氏について「彼が英語の先生になっていなかったら、サンコーシャU.S.A.はたぶんなかったんじゃないかな。彼は日本人以上に日本人のメンタリティを持っていて、時間にも正確だし、誠実だし、誰よりも働き者だし、何よりも会社の売り上げや利益の事を考えている。彼は社員たちの事もいつも考えながら活動してくれているので、それがやはり力ですよね」と話す。
今は日本、ヨーロッパの国々、オーストラリア、イスラエルでもシェア・ナンバーワンとなった。圭介氏は「何と言っても、我々は利益率の高い製品を作っているので、それがやはり一番ですかね」と語る。
現在、創業者の満幸氏は引退し、長男の裕介氏が三幸社の代表取締役社長としてホールディング会社とその傘下にある5つのディヴィジョンを総括して見ている。
次男の圭介氏はマーケティングを主に担当し、世界を回って世界のお客さんを繋げる仕事をしているという。
自動洗車機を見て触発され、ノンプレスフィニッシャーの製品化を実現した打越圭介副社長
新製品のノンプレスフィニッシャーも圭介氏が、次々に自動車を機械の中に入れて洗車をするアメリカの洗車機から思い付いた仕上げ機械だった。次々に衣類を機械に通して乾燥と仕上げをするれば、1時間に数百枚の衣類を仕上げることができる。水洗いできる衣服が主流になって来た現在、クリーニングに出す衣類は減って来たが、クリーニング店が手頃な値段でサービスを提供してくれれば、カジュアルでもシャツはクリーニング店に持って行きたい。ノンプレスフィニッシャーの導入によって大量の仕上げが可能になり、同時に人員を削減できれば、クリーニング店は消費者のニーズに応えると同時に利益を上げる事ができる。
圭介氏はこのアイディアを兄の裕介氏と話し合い、数年をかけて実現した。「メーカーがクリーニング屋さん達に利益を上げる努力をさせてあげられるぐらいのソリューションを用意しているか否かで、彼らの運命も決まってしまう訳なので、そういう機械がこれから必要であろうという考えから、そいう機械を作ったというのが流れなんですよ」と圭介氏は話す。
一方、ハイエンドの人々を対象にして利益を出しているクリーニング店もある。リモートワークで減りつつはあるものの、やはりアメリカのビジネスマンはコットンのワイシャツを着ていて、ワイシャツはクリーニング店の利益の源泉となっている。消費者はワイシャツと一緒にスーツや婦人物のドレスを持って来てくれるからだ。
クリーニング業を熟知している三幸社は、どの様な機械が求められているか良く知っている。ワイシャツの仕上げ機は三幸社の主力商品の一つであり、女性用のブラウスやドレスの仕上げ機も取り揃えている。この様な製品のラインアップにより、初期には入らなかったハイエンドの顧客を持つクリーニング店にも入るようになった。圭介氏は「最終的にオリジナリティの高い機械を作るようになりました。それが現在の我が社の礎になっているのは間違いないですね」と語った。